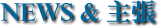
![]()
「解放新聞」(2025.05.05-3137)
2025年度部落解放・人権政策確立要求第1次中央集会を5月22日、東京・日本教育会館でひらく。昨年5月に成立した「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(「情報流通プラットフォーム対処法」。以下「情プラ法」)が4月1日に施行された。野放し状態にあるインターネット上の部落差別などの人権侵害等に関し、大規模プラットフォーム(以下PF)事業者に対応の迅速化等が義務づけられ、「被害者救済」の道筋も一歩前進したといえる。まずは「情プラ法」の趣旨・目的の理解を深め、広く周知・啓発を図ることが肝要だ。インターネット上の差別等の根絶へ「情プラ法」を積極活用し、新たな法制度の整備をめざすためにも、部落解放・人権政策確立要求運動をさらに前進させたい。
今年は「部落地名総鑑」差別事件が発覚して50年だ。当時、200社を超える大手企業や個人が購入し、結婚や就職時の身元調査に悪用されていた。総理府総務庁長官が「同和地区住民の就職の機会均等等に影響を及ぼし、その他さまざまな差別を招来し助長するという悪質な差別文書が発行され、一部の企業においてはそれが購入されたという事件が発生したことは、まことに遺憾なことであり、きわめて憤りにたえない」との談話を発表。明確に「差別書籍」と断言した。
ふり返れば「出版の自由」と、「差別書籍」が差別身元調査に悪用されて引き起こされる部落差別との闘いでもあった。そしていま、ネット上の「表現の自由」とどう向き合い、部落差別をはじめとする人権侵害をなくすルールづくりなどをどう創造していくのかが、ポイントの一つとなっている。
さて、昨年12月19日から今年1月23日まで総務省「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」などについてパブリックコメントが募集された。「情報流通プラットフォーム対処法第26条に関するガイドライン案」(以下「法26条ガイドライン」)に、各都府県連を通じ、支部や共闘団体、行政や企業団体などから多くの意見などが寄せられたことに感謝を申しあげたい。
「法26条ガイドライン」のなか、部落差別問題では、関連裁判例の一つとして一昨年6月28日に出された東京高裁の判決文(昨年12月4日付で上告が棄却。以下「確定判決」)の一部を引用して例示された。部落差別は「社会通念上受忍すべき限度を超えた精神的苦痛が生じた場合には、私生活の平穏などの人格的利益の侵害が成立する」という「私生活の平穏」を脅かすものと規定された。とはいえ「確定判決」は例示として示されただけであり、削除の対象となる具体的な部落差別の情報(投稿)等が例示されていない。
そこで、「情プラ法」による「個人として各々が削除を要請することができる」等の周知啓発を徹底的に広げることが重要だ。インターネット上で部落差別に係る情報が流布され、「社会通念上受忍すべき限度を超えた精神的苦痛が生じた」ことを当事者が訴える(申し出る)ことができる窓口を最大限活用しよう。
具体的には、まず、被差別部落の所在地情報(識別情報の摘示)に係る情報の削除を求める行動を提案したい。法務省・地方法務局では「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件および処理について」(依命通知・法務省権調第15号。2019年3月8日)にもとづいて「識別情報の摘示」を中心に削除のとりくみがされているが、削除されていない事案もある。現在、埼玉・新潟・大阪を中心に「部落探訪」削除裁判闘争を展開しているが、法務省・地方法務局、そして「情プラ法」を活用して「識別情報の摘示」削除のとりくみをねばり強く積み重ねることが大事だ。
あわせて施行された「情プラ法」における「大規模PF事業者の義務に関するガイドライン」(以下「法解釈ガイドライン」)では、「侵害情報調査専門員」の選任要件や、権利侵害や法定違反に該当する情報への対応について、削除要請から7日間のうちに削除の有無と理由を通知することなどが決まった。「被侵害者以外の者による削除申出」に関しては、「権利侵害情報による被害者を救済する観点から(中略)法第22条から第25条までの規定に準じて、速やかに対応を行うことが望ましい」と示されている。
いくつかの地方自治体と人権関係機関では、インターネット上の差別書き込みのモニタリングを実施し、部落差別をはじめとする書き込みや動画の削除のとりくみをすすめている。モニタリングで発見した権利侵害情報の削除を要請した場合、大規模PF事業者が対応するか、現時点では不透明だ。「法解釈ガイドライン」をふまえて「被害者救済」の道筋を広げるためにも、被害者を代行して公的機関等が削除を請求できる仕組みづくりなどが懸案課題である。
一方、今年1月28日から2月26日まで、法務省「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)中間試案」(以下「中間試案」)のパブリックコメントが募集され、中央本部も意見の集中をよびかけた。中間試案ではインターネット上の人権侵害を「課題横断的な人権課題に対する取組」として新たな項目立てがされている。インターネット・リテラシー(メディア・リテラシー)や情報モラルなど、あらためて「人権教育」「人権啓発」のあり方を問い直す時機にきているのではないか。日本は、国連「人権教育のための世界計画」(以下「世界計画」)の共同提案国だ。「世界計画」では、人権教育に関して▽人権について学び、日常生活で人権を行使するスキルを身につける▽人権尊重の姿勢、価値観および信念を進展又は強化させる▽人権を擁護し、促進する行動をとる―などが強調されている。偽・誤情報、なりすまし広告と詐欺、誹謗中傷や人権侵害、属性にたいする偏見等の流布など、これらの脅威にたいする基本的態度をどう身につけるかは、学校教育だけでなく社会教育、生涯教育の視点で問うことが重要だ。地方レベルでも「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」にもとづいた都道府県・市町村の行動計画の改定など、教育・啓発の充実・強化にとりくもう。
「情プラ法」施行をたしかな一歩とし、包括的差別禁止法と国内人権機関の整備をめざして、運動を着実に前進させることも確認しておきたい。中央本部としては、「情プラ法」の具体化とあわせ、個別法である「部落差別の解消の推進に関する法律」に「インターネット上の部落差別の禁止」などを規定した改正を見すえて、関係省庁および院内での働きかけなどにねばり強くとりくむ。
現在、20の都府県で人権尊重に関する条例(以下、人権条例)が制定され、部落差別に関する条例が8府県、インターネット上の誹謗中傷等に関する条例が2府県で制定されている(2025年3月24日現在・一般財団法人地方自治研究機構調べ)。人権条例のなかに「部落差別など不当な差別を禁止する規定」や「インターネット上の誹謗中傷等を禁止する規定」を盛り込んでいるところもある。「情プラ法」施行による法の趣旨・目的等の普及啓発、インターネット・リテラシーの課題等を念頭に置いた相談・支援体制の充実、被害者への支援など、「条例」の制定・改正を視野に入れたとりくみをよびかける。めざすべきは包括的な差別禁止法であり、独立した国内人権機関の整備である。中央本部としても、地方でのとりくみが積極的に推進されるよう財政的支援を関係省庁に求める所存である。地方レベルで「情プラ法」を積極活用したとりくみから立法事実などを積みあげ、さらに法制度の充実を求める運動を展開しよう。
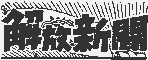
「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 180円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)